博士の愛した数式を読んでから、自分はすっかり小川洋子さんの小説を信頼しています
今回は、“コロナ禍で世界を揺らぎを体験した私たち
人の根幹にあるものを問う1冊”と帯に書いてあった、小川洋子さんの密やかな結晶を読んでみました
冒頭、場面展開、感想の流れで書いていきたいと思います
冒頭
物がひとつずつ記憶から消失していく島があり、主人公はその島に住んでいる小説書きの女性です
その島には秘密警察という組織があり、記憶から消えた物を住人が隠し持っていないか、そして記憶が残っている者がいないか探しています
記憶から消失した物を隠し持っている人、記憶が残り続けている人を、秘密警察は捕まえ、何処かへ連れ去ってしまいます
どこに連れて行かれるのかは誰にも分かりませんが、二度と会えなくなることがほとんどでした
主人公の母は、記憶が消失しない人だったため秘密警察に連れ去られ、父も亡くなりました
そのため、主人公の理解者は、昔からの付き合いのおじいさん、そして小説の編集者のR氏の2人だけでした
しかしそんななかで、R氏から自分は記憶が消失していないことを打ち明けられます
場面展開
主人公は、小説の理解者であるR氏を助けたいがために、自宅の2階と1階の間に隠し部屋をおじいさんと作り、匿うことにしました
首尾良く準備は進み、秘密警察にばれることなく、匿うことに成功します
R氏は奥さんとお腹の子に会えなくなってしまいましたが、またいつか会えることを祈ります
R氏が隠れ部屋にいる間も、島では消失が起こります
写真、木の実、カレンダー、春、小説
そして地震による津波で流されてしまったおじいさんのフェリー
そして、その時の後遺症によるおじいさんの死
左足の消失
右腕の消失
実際に物はそこに存在しているはずなのに、自分の記憶からは抜け落ちているのです
最後、主人公は声だけ残り、身体は隠れ部屋に残したままその後消滅、秘密警察もいなくなり、R氏は隠れ部屋から出て行きました
感想
近年のコロナ禍の世の中、当たり前にあった日常がなくなっています
そしてこの本の主人公も、日常の何かが消失していきます
個人的にはおじいさんの死が1番悲しかったのですが、少しづつ記憶から何かがなくなっていく様子は、日常化してしまえば取るに足らないことのように思えますが、
それはそれで、なんだか悲しいなと感じました
この小説は1999年に刊行されましたが、なんともいえないコロナ禍でのこの気持ちを、この小説はうまく表しているように思います
それでは読んでいただき、ありがとうございました
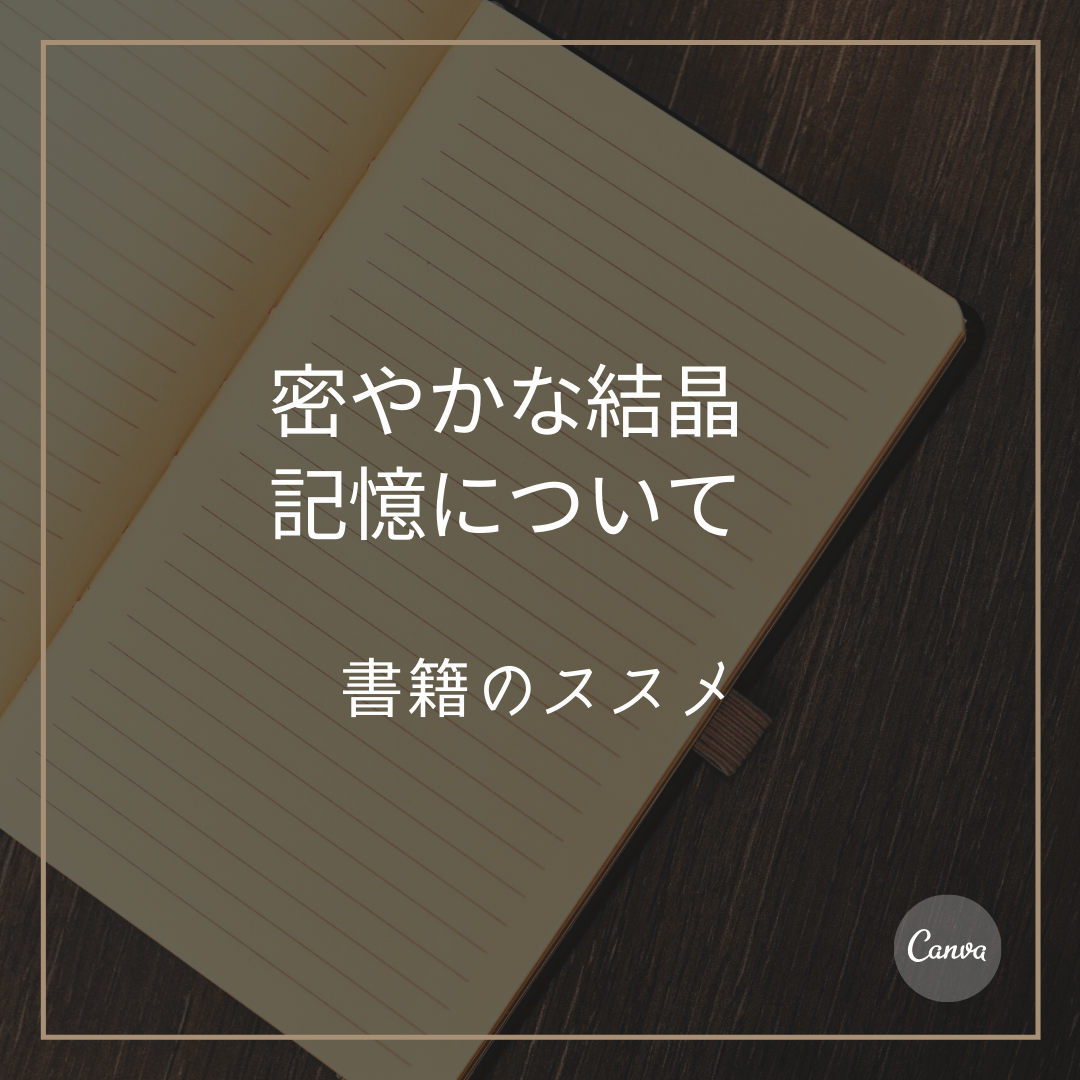



コメント